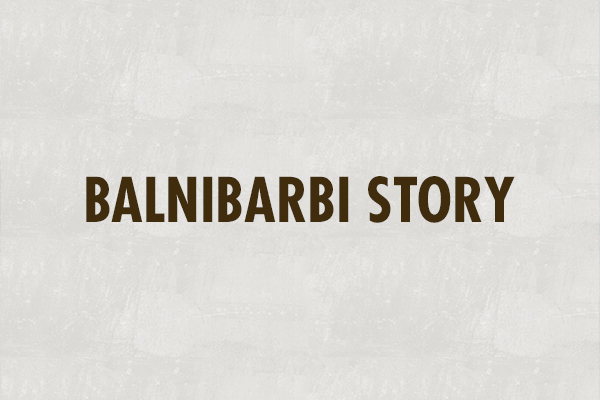株式会社バルニバービ 営業本部 運営推進部 山下正博。
クラシカルな店で培った確かな技術と、そこにいるだけでキッチンが華やぎ、人を楽しい気分にさせる才能はバルニバービで花開いた-。
高校を卒業後、料理人デビュー。21歳の時に鹿児島から上京し、複数の店で努力を重ねて、30歳でバルニバービへ。失敗を糧にグッドモーニングカフェを当社の看板カフェに育てあげた山下は、その手腕を買われて人材の発掘・育成という重要ポストに就いた。
「人を軸に成長している会社。会社の未来を担うポストなのでやりがいがあるし、可能性を秘めた人たちとかかわる毎日は楽しい!」と、実に楽しそうに話す。店づくりから会社の未来づくりへ、任されるフィールドが広がっても自身の持ち味を生かして自由闊達に指揮する山下に、料理人人生の中で培ったポリシーを聞いた。
僕の料理を喜んで食べてくれる人がいる。それが原点
山下が料理に興味を持ち始めたのは小学校低学年の頃。夕飯の支度をするお母さんの手伝いをしたのがきっかけだ。
「共働きだったので、『手伝って』と言われたからやるのではなく、自分からよく手伝っていましたね。そのうち見よう見まねで作った料理を『おいしいね』と言って食べてくれる人がいるのが嬉しくて、自分で工夫して作るようになりました」
探究心旺盛。しかも器用な山下はみるみるうちに腕を上げた。
「中学生の頃にはお肉を焼いてソースや付け合わせの野菜を作るくらいのことはやっていましたね。カレーもルーは使わず、どんなスパイスをどう使えば本格的なカレーができるのかを調べて、考えて、作ってはご近所に配っていました。自慢したかったんでしょうね(笑)」
食材の調達も自分で行った。近くのスーパーで手に入るものは限られているため、時折お母さんと街に出た時に大きなスーパーの食料品売り場を歩き回り、食材や調味料を物色するのが楽しかったという。
「母が買い物好きだったので『何時にどこで待ち合わせね』みたいな感じで分かれますよね。僕はおもちゃ売り場でゲームソフトを見ることもあったけど、多くの時間を食料品売り場で過ごしていました。ゲームソフトは『おこづかいで買いなさい』と言われましたが、料理に関するものは大概買ってくれましたね。母も食に興味のある人で、僕の料理を楽しみにしてくれていたんです」
父の反対を押し切ってプロの料理人に
料理が職業と結びついたのは「料理の鉄人」という番組がきっかけだった。グランシェフが色鮮やかなコックコートを着て登場し、テーマ食材を使ったオリジナル料理で対決する、当時の人気番組だ。
「シェフがかっこ良くて、進路を決める頃には調理科のある高校に行って料理を基礎から学びたいと思っていました」
厳しいお父さんに覚悟を決めて気持ちを伝えると猛反対された。料理が好きな一方、サッカー少年で、友だちづき合いが上手な我が子の幸せは、別の道にあると考えていたからだ。
「料理の世界は厳しいし、週末が忙しい仕事。友だちとも遊べなくなるぞ。本当にできるのかと問いつめられました。反対を押し切って自分の望みをかなえたので、もう後には引けないですよね。今思うとそのやりとりがあったから、どんなに辛くても弱音を吐かずに頑張って来られたのかなと思います」
3年間、1日も欠かさず鍋を磨く
高校を卒業後、最初に勤めたのは鹿児島のホテルの小さなレストランだった。高校時代、ホールのアルバイトをしていた割烹料理店の料理長の紹介だ。「洋食をやりたい」という希望がかないワクワクして入社したが、初日からプロの洗礼を受けた。
「1日中、立ちっ放しが辛かったです(苦笑)。体ができるとようやく料理に集中できましたが、店のペースに合わせて、一定のクオリティで料理を作ることの難しさを味わいました」
言われたことは理解できるが、イメージしているスピードに自分の手先がリンクしない。料理長の料理に到底及ばない。
「未熟だったので、うまくいかない原因が自分の技術不足にあることに気づいてなくて、なぜできないんだろうと悶々としていました。(自信があったので)生意気なことも随分言っていましたね」
そんな山下に課せられたのが鍋磨きだった。
「料理長から『自分のメンタルをコントロールできない奴にいい料理は作れない。持続性を大事にしろ。(ランチとディナーの間の)休憩時間に少しでも自分のできることをやれ』と言われて、毎日、鍋を1つ磨きました」
腑に落ちていたわけではなかったがやるしかない。父の手前もあり、根をあげるわけにいかなかった山下は、次の店に移るまでの3年間、1日も休まずにやり遂げた。
「技術を磨く前に心を磨け、という教えは今も心の支えになっています」

美しい皿は美しい環境の中からしか生まれない
情報が豊富な時代になり、今は働く場所を探すにしても、料理を学ぶにしても困らないが、山下が駆け出しの頃は怒鳴られる、たたかれるは当たり前だった。下手なやめ方をすれば噂が広まり、次の働き口を見つけにくくなる。味付けや調理方法もたやすく教えてくれないため、シェフに気づかれないところで盗むしかなかった。
本格的な料理を学びたくて21歳で上京した山下が、最初に門をたたいたフランス料理店も修行の場だった。細かい所作が無意識にできるようになるまで厳しくたたき込まれた。
「シェフが“美しい皿は美しい環境からしか生まれない”という発想だったので、ラップの張り方1つとってもピシッと美しく張っていないと叱られました。苦戦したのはちょっと切りものをした時に包丁やまな板を拭くタオルです。その都度たたんでまな板の左隅に置くのですが、忙しいとついたたむのを忘れてしまうんですよね。シェフはそれを見逃さないのでしょっちゅう叱られていました。無意識にできるようになるまでに、半年くらいかかったんじゃないかな」
キッチンの掃除も手抜きはもってのほか。換気扇やコンロの五徳なども毎日掃除した。
「慣れるまではきつかったですよ。料理以外の仕事は嫌いだったので…(苦笑)。でも、毎日やっていると習慣として身についてきて、汚いとストレスを感じるようになりました」
負けず嫌い全開でライバルに挑む
シェフと2人でキッチンを回していたため、朝6時に出勤して仕込みをし、休む間もなく仕事をして終電で帰る毎日。
「過酷だったので、いつ辞めてやろうか、そればかり考えていました(笑)」
そうは言っても2年間辛抱し、そこの料理を一通り習得したところで、当時流行っていたカリフォルニアキュイジーヌの店に転職した。東京で働く高校時代の友人の紹介だった。
「フレンチをベースに、自由な発想で料理を作るシェフで、当時の僕にはめちゃめちゃ衝撃的でした。斬新さに圧倒されました」
キッチンには6人の料理人がいた。23歳の山下が一番若かったが、初めて年の近い人たちの働きぶりを間近で見ることができる環境で、持ち前の負けん気が発動した。
「先輩方はかわいがってくれるんですよ。でも僕は1、2歳上の先輩方を勝手にライバル視して、常に抜かそうとギラギラしていました(笑)」
そこは自分の役割を果たしていれば、比較的なんでもやらせてくれた。だから定時よりも早く出勤し、急いで自分の仕事を終わらせて、先輩の仕事を分けてもらうことが日課になった。
先輩の料理人よりも格上の仕事を任される喜びがモチベーションとなり急成長したが、ただ1人、超えられない人がいた。
「自分もストイックな部類に入ると思うのですが、1つ上の先輩がものすごく芯のある人で、かなわなかったですね」
どんなに努力しても一番になれない現実を目の当たりにして、山下は初めて全力で走ることをやめた。
決して力が劣っているわけではない。人には向き不向きがあるということ。そう解釈したが、心は晴れなかった。
店と人との出会いが料理人を育てる #2 「バルニバービへの入社。挫折と気づき」へ続く
WRITER BALNIBARBI GROUP
バルニバービグループで食を通して「なりたい自分」を体現している仲間、「なりたい自分」を邁進している仲間、「なりたい自分」を見つけようとしている仲間のリアルな今の思いや、食に通ずる情報を発信していきます。
お店の業態は違っても、「ライフスタイルに自然に溶け込む地域に根ざした店づくり」というコンセプトは同じ。
その想いに沿ったどこにもない価値を提供しています。
「道のある所に店を出すのではなく、店を出した後にお客様のくる道が出来る」
それが私たちの目指す姿です。