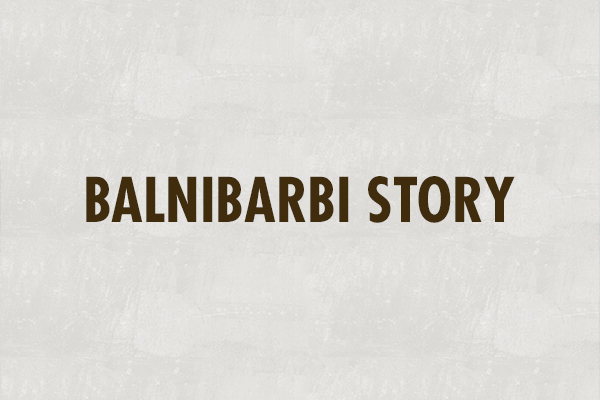バルニバービ入社の決め手になったもの
26歳でその店を辞めると、張りつめていた糸が切れたように気ままに過ごした。
「炭で焼いた焼き鳥とワインをマリアージュした店だったり、恵比寿のバーのキッチンだったり…。人づてにおもしろそうな店があれば行ってみて、そこで働くという感じでした」
基本的に料理が好き。人と会話をするのが好き。だから「どの店も楽しかった」というが、6件、店を変えても打ち込むものには出会えず。上京した時に描いていた「30歳までに鹿児島に帰って自分の店を持つ」という夢も、料理人のプライドもしぼみ始めていた。
「豪快で、人づきあいいい母が店を持つことを楽しみにしていたので、いつかかなえてあげたいと思っていたんですけどね」
ただただ、時間だけが過ぎていく……。バルニバービと出会ったのはそんな時だ。30歳になっていた。
「当時、
東京タワーの下で営業していたガーブピンティーノがいい店だと聞いて、お客としてランチを食べに行ったんです」
信頼している人の紹介であっても、その店に足を運び、自分の目や舌で確かめるのがマイルール。
「店の内装はオシャレだし、かかっている BGMもすごくかっこよくて、こんな店があるんだと驚きました。
シェフ(松城泰三/現在は神田のガーブピンティーノに勤務)が出て来てくれて話をすると、同い年でしっかりした人だったので腕前が気になるじゃないですか(笑)。『フルコースを食べたい』と言うと『ぜひ来て』と言ってくれたので次の日に行きました」
満席だったため急ごしらえの席だったが、松城シェフの作った料理が決め手になった。
「しっかり作られていて、すごくおいしかったんです。スタッフもいきいきと楽しそうに働いていて、おもしろそうな店だなと思いました」

当時の東京タワー下のGARB pintino
いきなり店を任されることに
バルニバービに入社して最初に配属されたのは、フルコースを食べたガーブピンティーノだった。まもなく店を任された。千駄ヶ谷の店(2010年4月オープン/グッドモーニングカフェ)がオープン準備に入っていて、ガーブピンティーノの松城シェフがそのメンバーに入っていたからだ。
「突然シェフが抜けて、20歳の女の子と、中堅の男の子と僕の3人で営業することになったんです。しかも、何の引き継ぎもないんですよ。今思えば、そういうところもこの会社らしいところなのですが、当時は面食らいました」
会社側の人を見る目と、料理人一人ひとりが自分の店という意識をもって働く風土だからこそ、こうしたサプライズ人事が可能なのだが、店を背負った経験がなかった山下は不安を打ち消すことに必死だった。
「こう見えて慎重派なんです(笑)。任せてもらった以上、きちんとやらなければ気が済まないので、しばらくは肩に力が入っていました。でも、日を重ねるうちにいろいろなことができるようになって、楽しむことができました」
心の寄りどころとなったのは、佐藤裕久社長から直に聞いたバルニバービへの熱い思いや店作りへの考え方だ。山下は、社長から自身が歩んで来た道や会社のこと、店づくりへの考え方、店の在り方やそこに立つスタッフとして必要なことなどを聞いていた。店を訪れた社長にランチを提供した際に挨拶すると、社長のほうから深い話をする機会を作ってくれたのだ。
社長が身近であることと、心に響いたその時の言葉(考え)は、今もまったく変わっていない。
まさかの落とし穴
貸借契約満了により、ガーブピンティーノは2010年9月に閉店した。無事に大役を果たした山下は、久しぶりに充実感を味わっていた。そこに新店のシェフという、新たなサプライズが飛び込んできた。2011年初旬のオープンを目指していた
蔵前の店(シエロイリオ)を任されたのだ。

蔵前のシエロイリオ3Fダイニング
見込みのある者は社歴にかかわらず引き上げていく、バルニバービの理念を肌で感じた山下は、野心に火を点していた。もう重要なポストを打診されてもたじろがない。自分がシェフとして店に立つ日を心待ちにして準備に臨んでいた。
ところがオープンまであと3日という時に、予想だにしない出来事が起きた。
「社長の判断でシェフから外されたのです」
今振り返れば理由は明確だ。シェフに必要な創造力(新しいものを生み出す力)が全く足りていなかった。
「新店を任せるといってもガイドラインは社長が決めるのが普通でしょう。僕は、言ってくれれば何でもやりますよ、というスタンスだったので、社長から『どんな店にしたいの』と聞かれた時に『それ、僕が決めるの?』って(笑)。根本の考え方から間違っていたのです」
バルニバービでは、店長やシェフがコンセプトからアイデアを出し、それをたたき台にブレストを繰り返して形にしていく。
「社長が言うのは『いい店を作れよ』ということだけ」
だから、普段からアンテナを張り、アイデアを練ったり、自分の考えをブラッシュアップしたり、感性を磨いたりしておくことが必要なのだが、当時の山下はそれができていなかった。
「お前の思いが乗っていなければいい店は作れない、という社長の言葉は胸に刺さりました」

Cielo y Rioのキッチン
もう辞めるしかない。追い詰められた日々
シェフを下ろされた山下は、オープンしたばかりの蔵前の店で一料理人として働くことになった。
「ホッとした反面、自分がシェフとして立つことになった時に他店から若い料理人を連れて来ていたので、どうにも格好がつかないですよね。その場から逃げ出したいけど、店はオープンしたてでめちゃめちゃ忙しかったので、落ち着くまでは我慢しようと自分なりに頑張っていました」
平静を装うにはできなかったことに対する何かしらの理由づけが必要だった。だから会社のせいにした。
「自分を守るためです。この会社は合わなかったと思うことで、心のバランスをとろうと必死でした」
そんな状態だから仕事を心の底から楽しめるわけがない。日に日に追い詰められていった山下は、メンタルのダメージがスキルに影響する、野球でいうイップスのような状態に陥った。
「味がブレるなど、今まで当たり前にできていたことすらできなくなったんです。そうなると周りの視線が気になって仕方がありませんでした。俺じゃない俺をどう思っているんだろうと…」
負の連鎖に陥り、どうにもコントロールできなくなった山下は、遂に退職を決心した。
料理人としてのプライドをかけて
辞意を伝えようと考えていたその日、偶然にも大阪から大筆総料理長がやってきた。総料理長に呼ばれた山下は、思わぬ話を持ちかけられた。
「
千駄ヶ谷で営業しているグッドモーニングカフェのシェフをやらないかと言うのです」
会社を辞めようと思っていることを伝えても総料理長は全く引かなかった。少し時間をもらって山下が出した答えは「シェフではなく一料理人として年内いっぱい働く」というものだった。逃げようとしていた自分を引き止めてくれた会社に、礼を尽くすような気持ちで「行くからには全力でやる」と返事をした。
そしてグッドモーニングカフェに職場を移すと、フレッシュな店、フレッシュな顔ぶれに気分が和らいだ。憑きものが落ちたように頭もスッキリして、いろいろなことを考えられるようになったという。
「次第にあの失敗とも向き合えるようになり、なぜ、そうなったのかを自分事として受け止めてからは早かったですね。自分が何をすべきかが見えてきて、アクションにつなげることができました」
自分が変わらなければ、他の店に移っても同じこと。
「心を入れ替えて、この会社でやり直すべきだーーー。そう考えて社長に頭を下げました」

事実は小説より奇なり
その時、山下はヨーロッパのカフェにいた。なぜ、海外で再起を誓うことになったのか。ことの発端は、いつものように仕事を終えて自転車で家路を急いでいる時に起きた偶然の出来事だった。
「一台の車に追い抜かれたのです。すれすれだったので冷やっとしたんですよね。その車が少し前で止まったので、追い越す際に運転席を見ると社長だったのです。驚きました」
近いうちに時間をもらい、もう一度この会社でやり直したいという気持ちを社長に伝えたいと思っていた山下は、「こんな偶然があるんだ!」と思い、すぐ引き返した。そして車の窓をコンコンとたたき、挨拶して「お話があるのでお時間をいただきたい」と伝えると、社長はこう言ったという。
「山下はたしか海外研修のメンバーに入っていたと思うから、その時に話そうと言うのです。年内いっぱいで辞めたいと伝えていた人間を、海外研修のメンバーに選びますか!?(笑)。驚きと申し訳なさとでいっぱいになりました」

研修の地、ロンドン、パリを巡りながら、その期待に応えたいという思いを強くしていく山下を、社長は頼もしく感じていたに違いない。同行していた企画部の北尾取締役から、社長の待つカフェを知らされて駆けつけた時には、もはや2人の間に多くの言葉は必要なかった。
店と人との出会いが料理人を育てる #3「料理人の本分と僕の仕事」 へ続く
WRITER BALNIBARBI GROUP
バルニバービグループで食を通して「なりたい自分」を体現している仲間、「なりたい自分」を邁進している仲間、「なりたい自分」を見つけようとしている仲間のリアルな今の思いや、食に通ずる情報を発信していきます。
お店の業態は違っても、「ライフスタイルに自然に溶け込む地域に根ざした店づくり」というコンセプトは同じ。
その想いに沿ったどこにもない価値を提供しています。
「道のある所に店を出すのではなく、店を出した後にお客様のくる道が出来る」
それが私たちの目指す姿です。
 当時の東京タワー下のGARB pintino
当時の東京タワー下のGARB pintino
 蔵前のシエロイリオ3Fダイニング
見込みのある者は社歴にかかわらず引き上げていく、バルニバービの理念を肌で感じた山下は、野心に火を点していた。もう重要なポストを打診されてもたじろがない。自分がシェフとして店に立つ日を心待ちにして準備に臨んでいた。
ところがオープンまであと3日という時に、予想だにしない出来事が起きた。
「社長の判断でシェフから外されたのです」
今振り返れば理由は明確だ。シェフに必要な創造力(新しいものを生み出す力)が全く足りていなかった。
「新店を任せるといってもガイドラインは社長が決めるのが普通でしょう。僕は、言ってくれれば何でもやりますよ、というスタンスだったので、社長から『どんな店にしたいの』と聞かれた時に『それ、僕が決めるの?』って(笑)。根本の考え方から間違っていたのです」
バルニバービでは、店長やシェフがコンセプトからアイデアを出し、それをたたき台にブレストを繰り返して形にしていく。
「社長が言うのは『いい店を作れよ』ということだけ」
だから、普段からアンテナを張り、アイデアを練ったり、自分の考えをブラッシュアップしたり、感性を磨いたりしておくことが必要なのだが、当時の山下はそれができていなかった。
「お前の思いが乗っていなければいい店は作れない、という社長の言葉は胸に刺さりました」
蔵前のシエロイリオ3Fダイニング
見込みのある者は社歴にかかわらず引き上げていく、バルニバービの理念を肌で感じた山下は、野心に火を点していた。もう重要なポストを打診されてもたじろがない。自分がシェフとして店に立つ日を心待ちにして準備に臨んでいた。
ところがオープンまであと3日という時に、予想だにしない出来事が起きた。
「社長の判断でシェフから外されたのです」
今振り返れば理由は明確だ。シェフに必要な創造力(新しいものを生み出す力)が全く足りていなかった。
「新店を任せるといってもガイドラインは社長が決めるのが普通でしょう。僕は、言ってくれれば何でもやりますよ、というスタンスだったので、社長から『どんな店にしたいの』と聞かれた時に『それ、僕が決めるの?』って(笑)。根本の考え方から間違っていたのです」
バルニバービでは、店長やシェフがコンセプトからアイデアを出し、それをたたき台にブレストを繰り返して形にしていく。
「社長が言うのは『いい店を作れよ』ということだけ」
だから、普段からアンテナを張り、アイデアを練ったり、自分の考えをブラッシュアップしたり、感性を磨いたりしておくことが必要なのだが、当時の山下はそれができていなかった。
「お前の思いが乗っていなければいい店は作れない、という社長の言葉は胸に刺さりました」
 Cielo y Rioのキッチン
Cielo y Rioのキッチン

 研修の地、ロンドン、パリを巡りながら、その期待に応えたいという思いを強くしていく山下を、社長は頼もしく感じていたに違いない。同行していた企画部の北尾取締役から、社長の待つカフェを知らされて駆けつけた時には、もはや2人の間に多くの言葉は必要なかった。
店と人との出会いが料理人を育てる #3「料理人の本分と僕の仕事」 へ続く
研修の地、ロンドン、パリを巡りながら、その期待に応えたいという思いを強くしていく山下を、社長は頼もしく感じていたに違いない。同行していた企画部の北尾取締役から、社長の待つカフェを知らされて駆けつけた時には、もはや2人の間に多くの言葉は必要なかった。
店と人との出会いが料理人を育てる #3「料理人の本分と僕の仕事」 へ続く