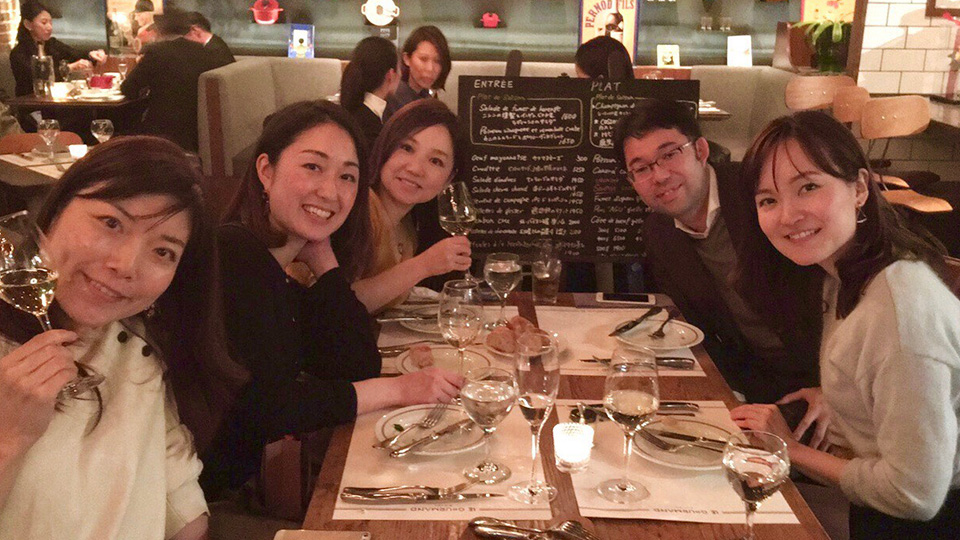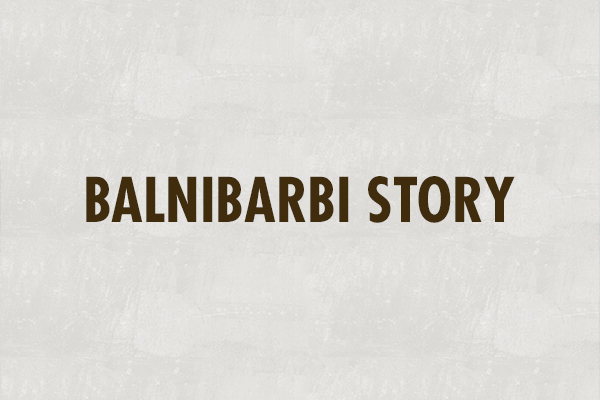4世代続くクビラシュヴィリ家の工房を訪問。カヘティ地方で最大の都市テラヴィから15分程度の村にある、外から見るとただの一軒家です。
今回クヴェヴリ職人にも会うことができて旅の序盤からテンションが上がります。
レニーとザザの父子が、年間に40個程度を製造しているそうですが、1個を仕上げるのに2か月もかかります。
サイズは20L~2000L程とかなり幅がありますが、2000Lの標準的なサイズで400ドル。手間暇を考えると、かなり安い。
手造りのため、大量生産は当然無理です。
全て手作りのオーダーメイドなので、サイズなどはワインメーカーが細かく指定できます。
どんなクヴェヴリを使うかによって、ワインの仕上がりに大きく影響するので
みなさん細かく指定されるそう。
これを聞いてからは各ワイナリーに訪問した際にはどんなクヴェヴリを使っているのか興味津々でたくさん質問させていただきました。
人によってこだわりポイントが違うので、何が一番良いのかはわかりませんでしたが、
ワインが漏れないようにするためのクヴェヴリの内側の加工や、
強度を上げるための外側の加工、更には焼き上げる温度まで様々な工夫がなされています。
4世代続くクビラシュヴィリ家の工房を訪問。カヘティ地方で最大の都市テラヴィから15分程度の村にある、外から見るとただの一軒家です。
今回クヴェヴリ職人にも会うことができて旅の序盤からテンションが上がります。
レニーとザザの父子が、年間に40個程度を製造しているそうですが、1個を仕上げるのに2か月もかかります。
サイズは20L~2000L程とかなり幅がありますが、2000Lの標準的なサイズで400ドル。手間暇を考えると、かなり安い。
手造りのため、大量生産は当然無理です。
全て手作りのオーダーメイドなので、サイズなどはワインメーカーが細かく指定できます。
どんなクヴェヴリを使うかによって、ワインの仕上がりに大きく影響するので
みなさん細かく指定されるそう。
これを聞いてからは各ワイナリーに訪問した際にはどんなクヴェヴリを使っているのか興味津々でたくさん質問させていただきました。
人によってこだわりポイントが違うので、何が一番良いのかはわかりませんでしたが、
ワインが漏れないようにするためのクヴェヴリの内側の加工や、
強度を上げるための外側の加工、更には焼き上げる温度まで様々な工夫がなされています。
 写真は完成後の1000L、そしてそのクヴェヴリに入って楽しむ某ソムリエ。
写真は完成後の1000L、そしてそのクヴェヴリに入って楽しむ某ソムリエ。私もスカートじゃなければ入りたかった…。笑 クヴェヴリはかつては地上に設置されていたそうですが、 地震で破損してしまったことがあったため(そりゃそうだろう)、 現在では地中に埋めて使われています。
 このクヴェヴリに収穫したブドウと酵母を入れ、蓋をすればワイン造りが始まります。
蓋はガラスのものや、スレートが多かったです。
そして、ジョージアのワイン造りの大きな特徴のひとつが、
ブドウの皮や種と液体(果汁からワインになった状態のもの)をクヴェヴリに入れておく期間が非常に長いことです。
そもそも通常の白ワインは皮や種を取り除いた果汁のみを発酵させてワインをつくりますが、
ジョージアでは白ワインも赤ワインも、皮も種も一緒にクヴェヴリに入れます。
そして通常ならアルコール発酵後すぐに、もしくは長くても数日以内に皮や種と液体は分離し、
上澄みを別の容器(木樽やステンレスタンク)に移して熟成させますが、
クヴェヴリに入れたブドウはアルコール発酵後も約半年はそのまま液体と一緒にしておきます。
これをマセラシオン、と言いますが、この長い期間で白ワインに皮の色が移り、
ゴールドに近いような、オレンジ色に近いような濃い色のワインとなるのです。
これが、最近注目されているオレンジワイン(アンバーワイン)です。
アンバーワインはどんな味がするのか、そのワインの造り手たちはどんな人なのか…
は次回に続きます。
このクヴェヴリに収穫したブドウと酵母を入れ、蓋をすればワイン造りが始まります。
蓋はガラスのものや、スレートが多かったです。
そして、ジョージアのワイン造りの大きな特徴のひとつが、
ブドウの皮や種と液体(果汁からワインになった状態のもの)をクヴェヴリに入れておく期間が非常に長いことです。
そもそも通常の白ワインは皮や種を取り除いた果汁のみを発酵させてワインをつくりますが、
ジョージアでは白ワインも赤ワインも、皮も種も一緒にクヴェヴリに入れます。
そして通常ならアルコール発酵後すぐに、もしくは長くても数日以内に皮や種と液体は分離し、
上澄みを別の容器(木樽やステンレスタンク)に移して熟成させますが、
クヴェヴリに入れたブドウはアルコール発酵後も約半年はそのまま液体と一緒にしておきます。
これをマセラシオン、と言いますが、この長い期間で白ワインに皮の色が移り、
ゴールドに近いような、オレンジ色に近いような濃い色のワインとなるのです。
これが、最近注目されているオレンジワイン(アンバーワイン)です。
アンバーワインはどんな味がするのか、そのワインの造り手たちはどんな人なのか…
は次回に続きます。